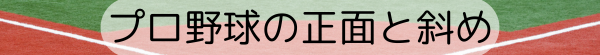先発完投からリリーフ重視の時代へ
かつてのプロ野球では、先発投手が試合を完投することが一般的でした。エースと呼ばれる投手は、最後まで投げ抜くことが当然とされ、球数や疲労よりも結果が優先されていました。しかし、近年では投手の役割が細分化され、リリーフやクローザーといった分業制が確立されています。その背景には、投手の負担軽減、戦略の多様化、データ分析の進歩といった要因があります。
投手分業制の流れが顕著になったのは、1980年代から1990年代にかけてのメジャーリーグの影響が大きいでしょう。日本のプロ野球でも、1990年代後半から2000年代にかけて、リリーフ専門のセットアッパーやクローザーが重視されるようになりました。
2000年代に入ると、先発投手は試合の中盤までの役割を担い、6回や7回からはリリーフ陣が継投するスタイルが一般的になりました。現在では、先発投手の投球数は100球前後が一つの基準とされ、完投数は年々減少しています。
この変化の背景には、選手のコンディション管理の重要性が挙げられます。過去にはシーズン中に300イニング以上を投げる投手もいましたが、現在ではそのような負担は考えられません。
医学的な研究やデータ分析の進歩により、投手の肩や肘にかかる負担が詳細に理解されるようになり、無理な投球を避ける傾向が強まりました。球団側も、エース投手を長く活躍させるために、投球回数の制限や休養日を適切に管理するようになっています。
リリーフ投手の重要性が増したことで、試合終盤の攻防がより戦略的になりました。セットアッパーとクローザーの役割が明確化され、リリーフ陣を整備することがチームの勝敗に大きく影響を与えるようになっています。
9回を任されるクローザーには、絶対的な安定感が求められ、短いイニングで圧倒的な投球を披露することが求められます。このように、継投の巧拙が勝敗を分ける場面が増え、監督やコーチの采配がこれまで以上に注目されるようになっています。
とはいえ、先発完投型の投手が完全に姿を消したわけではありません。近年でも、大エースと呼ばれる投手の中には、完投能力を備えた選手が存在します。しかし、それは例外的な存在となり、現代の野球においては、分業制のもとで複数の投手が役割を果たす形が主流になっています。この流れは今後も続くと考えられ、投手の起用法はより柔軟かつ緻密なものへと進化していくでしょう。